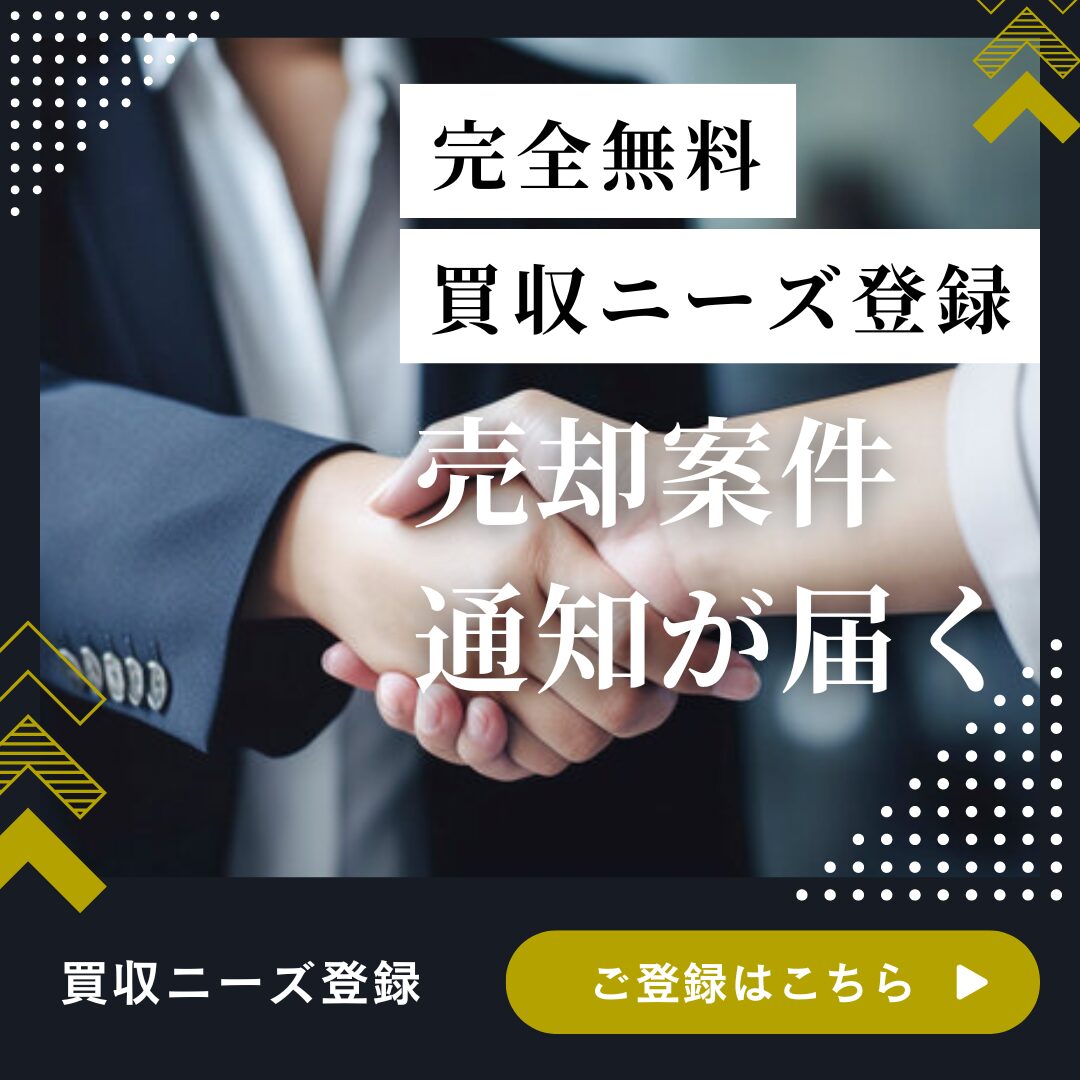「M&Aの事業譲渡ってどんなスキームなの?」
「事業譲渡の内容や特徴やについて詳しく知りたい」
この記事をご覧の方は、上記のような疑問をお持ちの人が多いのではないでしょうか。
実際に「M&A 事業譲渡」等と検索しても、信憑性に欠ける記事や専門家が執筆した解読が難しい記事しかなく、素人が目にしても理解できない記事が多いです。
そこで、今回はM&Aの専門企業である「M&A HACK」が、M&Aの事業譲渡について分かりやすく簡潔に解説します。
M&Aの事業譲渡のメリット・デメリットについても詳しく解説するので、M&Aに興味のある人は、ぜひ参考にしてください。
目次
M&Aにおける事業譲渡とは
事業譲渡とは、ある企業のすべての事業、あるいは一部の事業を買い手企業に譲渡するスキームです。事業譲渡では、事業そのものを譲渡するため、譲渡される対象には、通常、事業に関連する資産、負債、契約、従業員などが含まれます。
事業譲渡では、買い手側は特定の事業のみを引き継ぐことができるため、自社の事業成長に繋げやすいというメリットがあります。また株式取得や会社分割とは異なり、簿外債務などの不要な資産の承継を避けることが可能です。
ただし事業譲渡では、譲渡によって消費税が課されるなど税負担が大きくなります。また売り手企業は買い手企業の利益を保護するため、一定期間・範囲において譲渡した事業を行えない(競業避止義務)というデメリットも存在します。
M&Aにおける事業譲渡の目的
M&Aにおける事業譲渡の目的について解説していきます。事業譲渡の主な目的は、以下の通りです。
- 経営的リスクの軽減
- 資金の調達
- 事業の集中と効率化
それぞれ詳しく解説していきます。
経営的リスクの軽減
事業譲渡を行うことによって、経営的リスクを軽減することが可能です。特に売り手側(譲渡側)の企業は、不採算事業や将来的に成長が見込めない事業から撤退でき、経営資源(人材・資金・技術など)を本業や成長分野に集中させることができます。
負債の多い事業や将来的に投資負担の大きい事業を譲渡すれば、財務リスクを減らすことが可能です。さらに、譲渡による売却益を得ることで、財務状況の改善にもつながります。
また買い手側(譲り受け企業)にとっても、新たに事業を発足させることで、リスクの分散に繋げることが可能です。事業譲渡によって、複数の事業を運営することで、単一事業の不振を補うことができます。
経営資源の調達
事業譲渡は、数あるM&Aのスキームのなかでも、経営資源(人材・資金・技術など)の調達において非常に適した手法です。事業譲渡をおこなうことで、売り手・買い手ともに何らかの経営資源を調達することができます。
事業譲渡によって調達される最も代表的な経営資源は「資金」でしょう。これは売り手(譲渡側)の企業が買い手(譲り受け企業)から得られる代表的な経営資源です。事業譲渡によって資金を調達することで、別事業へ得た資金を投じることもできます。
また買い手側は、人材・技術・ノウハウなどの経営資源を手に入れることが可能です。特定の技術やノウハウを持つ事業を譲り受けることで、自社の競争力を強化することができます。
事業の集中と効率化
特に売り手側企業にとって、事業譲渡をおこなうことは、事業の集中と効率化に繋がる要素です。事業譲渡は、企業が経営資源を最適化し、競争力を高める手段となります。
事業譲渡により、収益性の低い事業や本業とシナジーのない事業を譲渡することで、経営資源を中核事業に集中することが可能です。逆に、買い手側は、必要な事業を譲り受けることで、経営の強化を図ることができます。
また非効率な事業を切り離すことで、人員や設備の運用コストを削減できる可能性が高いです。事業譲渡後は、スリム化した経営体制で意思決定のスピードが向上し、業務の効率化が進みます。
M&Aの事業譲渡における買い手のメリット・デメリット
事業譲渡における買い手側(譲り受け企業)のメリットとデメリットを解説していきます。
| メリット | デメリット |
|
|
買い手のメリット
事業譲渡における買い手側の主なメリットは、以下の通りです。
- 新規事業への進出
- 事業拡大のチャンス
- ノウハウや人材の獲得
それぞれ詳しく解説していきます。
新規事業への進出
事業譲渡を行うことによって、買収側企業は新規事業への参入を容易に行うことが可能です。一から新規事業として立ち上げるより、はるかに業界への早期参入が可能となります。
景気の悪化により単一分野での事業展開は非常に危険とされている現代において、M&Aによる新規事業への参入は非常にメリットが大きいとされている戦略です。リスク分散の観点からM&Aをする大手企業の数は、ここ数年で一気に増加しています。
また売却先の企業が持つノウハウや市場シェアをそのまま引き継ぐことができるため、総体的に見れば、新規事業への投資額を削減することにも繋がるでしょう。新規事業参入におけるコスト削減でも大きく貢献する要素となります。
事業拡大のチャンス
事業譲渡において買収側が得られる大きなメリットは、事業拡大のチャンスを得られることでしょう。事業譲渡によって買収側の企業は規模やシェアの拡大を狙うことができます。
事業譲渡においては、売手となる企業が持つ設備や建物のような有形資産に加え、顧客・取引先情報などの無形資産を手に入れることも可能です。特に、「取引先」「顧客情報」などの無形資産は実績に直結する要素であるため、事業譲渡による早期事業拡大も視野に入れることができます。
また多くの業界では大手企業の市場シェア率が高いですが、事業譲渡を行うことで自社の市場シェアを拡大させることが可能です。中小企業同士のM&Aを行うことで、大手企業に対抗する勢力を付けることにも繋がります。
ノウハウや人材の獲得
企業経営において事業成功のカギを握るのは、自社が持つ「ノウハウ」と「人材」です。これら2つが揃っている企業は、市場において高い競争力を得ることができます。競争が激化している現代の市場において、競争力の獲得は重要な要素でしょう。
もし事業譲渡によって事業の譲り受けを検討しているのであれば、まずは譲り受け先企業が持つノウハウと人材に目を向けることが先決です。事業譲渡によって現在の自社が持たないノウハウや人材が手に入るか否かをチェックしましょう。
また事業譲渡に関しては、買収先が持つ市場規模の如何によって、取引額に大きな差が生じます。より巨大な商圏エリアを所有している企業ほど、高値で取引されるケースが多いです。
買い手のデメリット
事業譲渡は買い手側に大きなメリットをもたらす一方で、デメリットが存在することも確かです。事業譲渡が買い手にもたらすデメリットは、以下の通りです。
- 粉飾が見つかる場合も
- 赤字発生のリスク
- 既存従業員の不満が発生する可能性
それぞれ詳しく解説していきます。
粉飾が見つかる場合も
事業譲渡の買い手にとって大きなリスクとなるのが、取引成立後に粉飾が発見されることです。M&Aにおける粉飾とは、会計の不正操作や虚偽の財務情報の開示など、取引前に把握できなかった買い手にとって不利な情報のことを指します。
売り手が抱える不利な情報は、M&A取引前のデューデリジェンスによって通常発見されるものです。しかし、どんなに高い精度のデューデリジェンスを行ったとしても、粉飾のリスクをゼロにすることはできません。
万が一、取引後に粉飾が発覚した場合には、自社のブランド価値が低下する可能性は非常に高いです。M&Aの買い手にとって粉飾はもっとも回避すべき事柄の一つと言えます。粉飾のリスクを低減させるためには、的確なデューデリジェンスが必須です。
赤字発生のリスク
M&Aによる事業の買収(譲り受け)は、企業の経営戦略として非常に有効な手段です。しかしM&Aによって事業を買収したからといって、必ずしも譲り受けした事業が好転に向かう保証はありません。場合によっては赤字が発生する可能性もあるので注意が必要です。
例えば、M&A後の統合(シナジーの実現)が予想以上に困難だった場合、統合に必要なコストが増加することがあります。システムの統一、組織文化の調整、社員のリストラなど、これらの費用が予想を超えると、買い手にとって一時的な赤字を招く可能性が高いです。
また買い手が買収した事業が財務的に問題を抱えている場合、その企業の赤字や負債が買い手の財務状況に影響を及ぼすことがあります。特に、買収後に事業統合やリストラがうまく進まなかった場合、予想以上にコストがかかり、収益が上がらないことがあります。
既存従業員の不満が発生する可能性
事業譲渡によって買い手企業の既存従業員に不満が発生する可能性は十分にあります。特に、買収された事業の文化や業務プロセスが大きく異なる場合、従業員は自分の役割や未来に対して不確実感を感じ、ストレスや不満が生じる可能性が高いです。
例えば、M&Aを通じて、異なる企業文化や価値観が一つに統合されることがあります。買い手企業の従業員が新しい企業文化に馴染むのに時間がかかる場合、価値観の違いや仕事の進め方の相違に対する不満が生じる可能性は高いでしょう。
またM&A後、昇進の機会やキャリアパスが不透明になることがあります。新しい組織構造や業務プロセスにより、従業員は自分のキャリアの未来について不安を感じることでしょう。買い手企業は従業員との信頼関係を維持し、M&A後の調整を慎重に行うことが重要です。
M&Aの事業譲渡における売り手のメリット・デメリット
M&Aの事業譲渡における売り手(譲渡企業)のメリット・デメリットを解説していきます。
| メリット | デメリット |
|
|
売り手のメリット
事業譲渡における売り手側のメリットは、以下の通りです。
- 事業の特定部分をターゲットにできる
- 資産や負債の整理が可能
- 売却益を得やすい
それぞれ詳しく解説していきます。
事業の特定部分をターゲットにできる
事業譲渡では、会社全体ではなく、特定の事業部門や資産だけを譲渡することが可能です。これは、会社分割や株式譲渡と異なり、譲渡対象を細かく選択できます。
事業譲渡では、売り手側が手放したい事業のみを対象に取引を行うことが可能です。例えば、「A事業だけを売却し、B事業は残す」といった選択をすることができます。
また「設備や従業員は含めるが、特定の負債は引き継がない」などの細かな調整ができることも事業譲渡のメリットになります。
ただし契約の相手方の承諾が必要になる場合があり、手続きが煩雑になるケースも多いです。事業譲渡は柔軟性が高い一方で、契約手続きの面で注意が必要なスキームになります。
資産や負債の整理が可能
事業譲渡により、売り手側の企業は、資産や負債の整理をおこなうことが可能です。譲渡対象の資産や負債を選別できるため、不要なものを整理しながら譲渡することができます。
事業譲渡では、事業に必要な資産のみを移転でき、不要な資産は除外することが可能です。例えば、「工場の設備は含めるが、不要な在庫は含めない」といった調整をおこなうことができます。
また事業譲渡では、負債は譲渡対象に含めなければ引き継がれないのが原則です。ただし、買い手との合意があれば、特定の負債のみを引き継ぐこともできます。事業譲渡を活用すれば、資産や負債を整理しながら効率的に事業を売却・再構築することができます。
売却益を得やすい
事業譲渡は数あるM&Aのスキームのなかでも、売却益を得やすいスキームのひとつです。株式譲渡では売却益は株主個人に入りますが、事業譲渡では会社に入るため、会社の資金繰りや再投資に活用することができます。
事業譲渡では、売却対象の資産・負債を個別に評価するため、買い手と交渉しやすく、高値で売却しやすいのが特徴です。特に、ブランド価値やノウハウ、取引先などの無形資産も含めた評価ができます。
また事業譲渡では、買い手側は不要な負債を引き継がず、魅力的な部分だけを取得できるため、他の買い手と競争になり、高値がつく可能性が高いです。事業譲渡は「売却対象を選択できる」「買い手のメリットが大きい」などの理由で、適切な交渉を行えば売却益を得やすいスキームです。
売り手のデメリット
事業譲渡では、売り手にとってもいくつかのデメリットが存在します。売り手にとってのデメリットは、以下の通りです。
- 買い手が見つからない場合も
- 事業規模の縮小
- 取引先との関係悪化のリスク
それぞれ詳しく解説していきます。
買い手が見つからない場合も
事業譲渡における売り手側企業にとって最も大きい懸念材料となるのが、買い手企業が見つからないケースです。M&Aは企業間同士の取引であるため、当然ながら相手企業(譲り受け企業)が見つからなければ、取引は発生することがありません。
買い手が見つからない理由としては、事業の市場価値が低いことが最も大きな要因であることが多いです。業界内で競争が激しく、他の企業にとって魅力的な買収対象がすでに存在している場合、売り手企業は見向きもされない可能性があります。
また売り手企業が経営不振や財務問題を抱えている場合、買い手にとってその企業を買収するリスクが高いとみなされ、売却が難しくなる可能性が高いです。特に赤字経営や借金が多い企業は、魅力的な買収対象として扱われにくくなります。
事業規模の縮小
事業譲渡により自社の事業の一部を売却した場合には、当然ながら自社の事業規模は縮小することになります。これはメリットでもある反面、大きなデメリットともなり得る要素です。
売却した事業が会社の主要な収益源であった場合、売上や利益が大きく減少し、経営基盤が弱まる可能性があります。さらに売却した事業が企業のブランド価値の一部を担っていた場合、市場や取引先からの評価が変わる可能性もあります。
さらに売却によって事業を担当していた従業員が譲渡先に移籍したり、残った従業員の不安が増してモチベーションが低下することも多いです。事業の一部を手放すことで、会社全体の経営戦略や方向性を見直す必要が生じます。
ただし、「不採算事業を切り離し、経営資源を成長分野に集中できる」「資金調達が可能になる」といったメリットがあるのも事実です。事業譲渡の判断には、メリットとデメリットを慎重に比較することが重要となります。
取引先との関係悪化のリスク
M&Aによって事業を売却することで既存取引先との関係が悪化するリスクがあります。これまで懇意にしていた既存取引先との関係性に変化が生じ、場合によっては取引が停止になるケースも珍しくありません。
M&A後は、経営方針や戦略が変わることに対する取引先の不安感が生じる可能性が高いです。特に、取引先が買収企業の方針に不安を抱く場合、関係が悪化することがあります。例えば、取引条件の変更や、供給体制、価格設定が変わることへの懸念があると、取引先は離れることを考えるかもしれません。
また買収企業が取引先との関係を重視していない、または異なる戦略を取っている場合、既存取引先に対して不満が生じ、契約の見直しや取引の中止が起こることもあります。M&A後に取引先との関係を維持するためには、慎重な対応と戦略的なコミュニケーションが重要です。
事業譲渡以外のM&Aスキーム
M&Aには、当然ながら事業譲渡以外のスキーム(手法)も数多く存在し、M&Aを実施するのであれば、他のスキームについても理解を深めておくことが重要です。
そこで、ここでは、M&Aにおける事業譲渡以外のM&Aスキームについて解説していきます。
買収
買収とは、1つの企業が他の企業を買い取り、支配権を得ることです。買収される企業は買収者によって支配され、経営が一元化されます。
M&Aにおける買収の主なスキームは、「株式取得」「事業譲渡」「会社分割」の3種類です。事業譲渡を除く、2種のスキームについて詳しく解説していきます。
株式取得
株式取得とは、ある企業の株主が自分が所有する株式を、他の個人や法人に譲渡することです。M&Aにおいては、最も一般的なスキームのひとつでもあります。株式取得の主な目的は、以下の通りです。
- 資本間提携や支配権の移動
- 資金調達
- 株主の移動
株主取得は、特に企業の経営権に関連する場面で用いられやすいスキームです。株式取得によって3分の2以上の株式を取得すれば、反対する株主を「スクイーズアウト」により強制排除することもできます。
ただし株式取得では、対価として現金が必要であることに加えて、不要な資産や簿外債務・偶発債務などを引き継ぐリスクがあるので注意が必要です。M&Aのスキームとしては比較的簡単な手法ですが、実施には相応のリスクも伴います。
会社分割
会社分割とは、ある企業のすべての事業または一部の事業を別会社に承継するスキームです。別会社が既存企業なら「吸収分割」、新設会社なら「新設分割」に分類されます。会社分割の主な目的は、以下の通りです。
- 事業の集中化と再編
- 経営の効率化と最適化
- 財務の健全化
会社分割では、一部の事業を承継する場合、買い手企業は関連のある企業だけを承継することができるため、シナジー効果を得やすいのがメリットです。同時に一部事業の承継により、売り手企業は事業のスリム化を図ることもできます。
ただし会社分割のスキームでは、買い手企業は、包括承継の仕組み上、会計帳簿に記載されていない簿外負債や、不要な資産なども引き継がなければなりません。また業種によっては、許認可の引継ぎができない場合もあるので注意が必要です。
合併
合併とは、複数の会社を1つの会社に統合するM&Aの手法です。合併は、複数の企業が互いに協力し、資産や負債を統合し、1つの企業として活動を開始することを目的としています。
合併の種類は「新設合併」と「吸収合併」の2つです。それぞれのスキームについて詳しく解説していきます。
新設合併
新設合併とは、合併対象となるすべての企業の権利や義務を、新しく設立した会社に引き継ぐスキームです。新設会社設立後は、対象となった企業は1社残らず消滅します。新設合併の主な目的は、以下の通りです。
- シナジー効果の最大化
- 経営戦略の統一
- 資本調達力の強化
新設合併では、合併対象企業が持つすべての権利義務を1社に集約させることができるため、合併によるシナジー効果を最大化させることが可能です。事業統合のスキームによって、ブランド力や資金調達力・開発力などのシナジー効果を得ることが出来るでしょう。
一方で、新設合併のスキームは、M&Aの実行までに時間とコストを要するため、スピード感がある取引を求める場合には不向きです。また新設合併では、吸収した企業の許認可を引き継ぐことができないため、許認可を取り直す必要があります。
吸収合併
吸収合併とは、既存の1社のみを存続させ、他の消滅企業が所有していた一切の権利義務を承継させるM&Aのスキームです。新設合併では、合併の対象企業は全て消滅しますが、吸収合併では1社のみ存続することになります。新設合併の主な目的は、以下の通りです。
- 規模の経済の実現
- 市場シェアの拡大
- 競争力の向上
吸収合併のスキームは、主に市場での規模や競争力を高める目的で行われることが一般的です。吸収合併によって、複数企業の機能がひとつの企業に集約されるため、高いシナジー効果を得ることができます。
ただし、吸収合併において、存続企業と消滅企業の取引先が重複している場合、トータルの収益・利益が減少するおそれがあるので注意が必要です。吸収合併のスキームで得られる権利内容をよく把握しておくことが重要になります。
提携
M&Aのスキームにおける提携とは、複数の会社が協力し合うことで、共通目的の達成を目指すM&Aの手法です。提携のスキームでは、企業が独自性を持ちながらも、互いに協力関係を結び、資源や能力を共有することを目的としています。
提携のスキームにおける種類は、主に「資本提携」と「合弁会社設立」の2種類です。それぞれのスキームについて詳しく解説していきます。
資本提携
資本提携とは、対象企業同士が出資を行い、株式を保有し合うことで、経済的・戦略的に協力する関係を結ぶことです。資本提携における主な目的には、以下のものが挙げられます。
- シナジー効果の発揮
- 共同戦略の立案と実行
- 資金調達の効率化
資本提携では、企業は外部から出資を受けることができるため、資金調達をより容易にすることが可能です。また資金だけでなく、技術力や開発力なども共有することができるため、高いシナジー効果を創出することができます。
ただし、資本提携は企業間同士で資本を共有することになるため、経営方針や戦略において提携先企業の意見や影響を受けやすくなるため注意が必要です。資金的・資源的優位性が得られるものの、経営方針の合致が困難となります。
合弁会社設立
合弁会社設立とは、2社以上の企業が協力し、新たな法人を設立するM&Aのスキームです。提携した企業が共同で出資し、その会社の経営権を分担して運営する形態になります。合弁会社設立における主な目的は、以下の通りです。
- 市場への新規参入
- リスク分散
- 規模の経済の実現
合弁会社設立は、互いの企業が出資をし合って新たな企業を創設するため、経営投資の目的が非常に大きいです。共同出資に近い形となるため、新規事業や市場への進出をリスク分散して行うことができます。
ただし、合弁企業を設立する際、提携する企業同士で目的や優先順位が異なることがあるため注意が必要です。特に、各企業が異なる市場戦略を持っていたり、異なる利益を追求している場合、利益相反が発生するリスクがあります。
M&Aにおける事業譲渡の流れ
M&Aにおける事業譲渡の主な流れについて解説していきます。事業譲渡の主な流れは、以下の通りです。
- 事前準備
- マッチング・交渉
- 経営陣同士の面談
- 基本合意契約の締結
- デューデリジェンスの実施
- 事業譲渡契約の締結
それぞれのフェーズについて解説していきます。
事前準備
M&Aの事業譲渡を円滑に進めるためには、事前準備が必須です。このフェーズでは、売却企業が自社の財務状況や事業内容を整理し、譲渡対象となる資産・負債、契約関係などを明確にします。
また、売却の目的や希望条件を定め、必要に応じてM&Aアドバイザーや弁護士、公認会計士などの専門家を交えて戦略を策定するフェーズです。
マッチング・交渉
買い手候補を探し、交渉を進めるフェーズです。売却企業はM&A仲介会社やアドバイザーを活用しながら、譲渡対象に関心を持つ企業とコンタクトを取ります。
候補先との初期的なやり取りの中で、双方の事業内容やシナジー効果を確認し、基本的な条件のすり合わせを行います。
経営陣同士の面談
買い手候補と売り手企業の経営陣が直接面談を行い、M&Aの意図や企業文化、経営戦略の適合性などを確認するためのフェーズです。
この面談では、双方の信頼関係を築くことが重要となります。また、譲渡後のビジョンや従業員の処遇について話し合われることも多いです。
基本合意契約の締結
基本的な譲渡条件が合意された段階で、「基本合意契約(LOI)」を締結するためのフェーズです。これにより、譲渡価格の概算、支払い条件、スケジュール、秘密保持義務などが明文化されます。
基本合意契約書は、買い手企業が、どのような内容・条件で事業譲渡を行いたいかを伝えるための提案書である「意向証明書」と、買い手と売り手双方の交渉内容をまとめた「基本合意書」の2種類です。
ただし基本合意契約が成されたといっても契約が完全に成立されたわけではありません。実際に基本合意契約後に契約が破談されたケースもあります。
デューデリジェンスの実施
買い手企業が売り手企業の財務、法務、税務、事業内容などを詳細に調査するフェーズです。デューデリジェンスにおける専門家が、財務諸表や契約書類、知的財産権、人事・労務関係の書類などを精査し、リスクを洗い出します。
デューデリジェンスで得た結果は、その後の取引内容に大きく変動を与えるものです。デューデリジェンスの内容を踏まえて最終的な譲渡条件の調整が行われます。
事業譲渡契約の締結
デューデリジェンスの内容を元に取締役会での決議を得た後は、いよいよ事業譲渡契約の締結に移行します。譲渡対象の資産や負債、契約条件、価格、支払い方法、従業員の処遇などが記載されるのが一般的です。
事業譲渡契約書の記載内容は会社法で定められているわけではありませんが、法的拘束力があるので注意が必要となります。
事業譲渡における税金と税務
事業譲渡をおこなうのであれば、税金と税務について理解しておくことが大切です。そこで、ここでは、事業譲渡における税金と税務について、買い手・売り手の双方から解説していきます。
事業譲渡の税金に対する買い手の留意点
事業譲渡における買い手側は、発生する消費税に加え、譲渡価額の取得価額や減価償却、移転試算に関わる税務リスクを確認しておくことが必須です。
事業譲渡では、譲渡対象の資産ごとに消費税がかかるかどうかが異なります。買い手側は仕入税額控除の適用を受けられるかどうかを確認し、消費税負担の影響を試算することが必須です。
事業譲渡では、買い手は個別の資産ごとに取得価額を設定するため、減価償却資産(建物・設備等)は適正な取得価格を基に減価償却費を計上することになります。営業権(のれん)を取得した場合、法人税法上は5年で均等償却が可能です。
また事業譲渡は原則として負債を引き継ぎませんが、未払金や簿外債務、未認識の税務リスク(税務調査リスク等)がないか、事前のデューデリジェンスが重要になります。事業譲渡後、譲渡対象の過去の取引について税務調査が行われた場合、買い手に影響を及ぼす可能性があります。
事業譲渡の税金に対する売り手の留意点
事業譲渡における売り手側は、事業譲渡により得た対価(売却額)から、譲渡する事業の簿価(帳簿上の資産価値)や譲渡にかかる費用を差し引いた譲渡益が発生した場合、法人税(法人の場合)または所得税(個人事業主の場合)が課税されます。
事業譲渡の対象に棚卸資産(商品・原材料など)や固定資産(機械・設備・建物など) が含まれる場合、それらは原則として消費税の課税対象です。ただし、「包括的な事業譲渡」に該当する場合は、消費税の課税対象外となる可能性があります。
また事業譲渡は 資産・負債・契約の個別移転 となり、会社全体を譲渡する 株式譲渡 とは異なるのが特徴です。
株式譲渡であれば、売り手は 譲渡所得課税(税率20.315%) で済みますが、事業譲渡の場合は法人税等の課税となるため、課税負担が高くなることがあります。
事業譲渡を成功させるためのポイント
事業譲渡を成功させるためのポイントについて解説していきます。事業譲渡を成功させるためのポイントは、以下の通りです。
- M&A戦略の立案
- 利害関係者の把握
- 売却価格の予測
それぞれ詳しく解説していきます。
M&A戦略の立案
M&A戦略とは、M&Aによってどのような効果を得るのかを検討するための準備や計画を指すものです。M&A戦略の如何によって、M&A後の事業計画もより具体化されます。
M&A戦略では、自社の分析(SWOT分析)や市場調査・業界トレンドなど様々な要素を調査することが必須です。明確な戦略を立てたうえで、買収(売却)先選定や交渉を行なっていくことになります。
M&A戦略において重要視すべきポイントは、以下の通りです。
- M&Aにより何を達成したいか(売却・売却後まで視野に入れたもの)
- 自社は売れるのか。売れるとすればどの部分か(事業の一部または全部)
- いつ・誰に・何を・いくらで・どのように売却(買収)するか
- 買収(売却)において障壁となる要素はあるか
- M&Aに必要な予算はどのくらいか(買収側のみ)
上記のポイントを押さえておくだけで、M&Aにおける戦略はより具体的なものになるはずです。反対にM&A戦略が場当たり的だと、交渉において不利な条件を飲まされるなどの弊害が発生します。
また自社にM&Aにおいて詳しい人物が所属していないのであれば、M&A委託業者に戦略の立案・実行を依頼することを強く推奨します。費用こそ掛かりますが、よりスムーズにM&Aを成功まで導いてくれるでしょう。
当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。
無料相談のご予約:
https://sfs-inc.jp/ma/contact
利害関係者の把握
M&Aにおいて、利害関係者の把握は非常に重要です。M&Aは単なる企業間の取引ではなく、さまざまな関係者が絡む複雑なプロセスであり、その利害を理解し適切に調整することが成功への鍵となります。
利害関係者の理解が不足していると、後々の問題や紛争を引き起こし、取引が失敗に終わる可能性も高いです。例えば、株主は企業の最も重要な利害関係者の一つとなります。特に上場企業の場合、株主の意向がM&Aの成立に大きな影響を与えることがあります。
また企業の経営陣は、M&Aにおけるもう一つの主要な利害関係者です。 経営陣は通常、企業の方向性を決定する立場にあります。M&Aを通じて企業の経営権が変わることもあるため、経営陣がM&Aを支持しているか、または反対しているか、その理由を明確に理解することが重要です。
売却価格の予測
M&Aを行う際には、あらかじめ凡その売却価格を予測しておくことが大切です。M&Aによって自社の売却を考えている場合には、本取引移行前に売却価格の予想を行っておきましょう。
売却価格を予測するためには、企業の価値をどのように評価するかが重要です。売却価格の予測には「DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)」や「類似企業比較法(マーケットアプローチ)」の手法が用いられます。
特に類似企業比較法は、類似の業種や規模を持つ規模を持つ上場企業の株価やM&A取引の事例を元に、対象企業の価値を予測するため、比較的容易に売却価格を予測することが可能です。精度は下がりますが、インターネット上でも情報をキャッチすることができます。
M&Aの事業譲渡における成功事例
M&Aの事業譲渡における成功事例を紹介していきます。
帝欧オートとサン・ガレージによるM&A
2017年5月に、帝欧オートがサン・ガレージの保有するディーラー業を譲り受けしたM&Aの事例です。本取引は、事業譲渡のスキームが用いられましたが、譲渡金額は公開されていません。
譲り受け企業である「帝欧オート」は、ウルトラプラスホールディングスの連結子会社として、「VOLVO(ボルボ)」正規ディーラー事業を中心に輸入車販売・自動車整備・各種自動車用品販売を手掛ける企業です。一方の譲渡企業である「サン・ガレージ」は、同じく「VOLVO」のディーラー事業を運営しています。
本件M&Aは、共通の自動車ブランドを扱う自動車小売(ディーラー)企業同士の取引事例です。同業者同士が取引を行うことにより、更なる事業内容の充実と収益基盤の拡大を目的としています。
ジーニーとデクワスによるM&A
2023年6月に、株式会社ジーニーは、サイジニア株式会社のグループ会社であるデクワス株式会社の運営するネット広告サービスの事業を譲渡したM&Aの事例です。本取引は、事業譲渡のスキームが用いられました。
譲り受け企業である「株式会社ジーニー」は、広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、海外事業を行っている企業です。一方の譲渡企業である「デクワス株式会社」は、インターネットメディア事業、インターネット広告代理事業等を行っている企業になります。
本取引は、ともに広告・マーケティング事業を運営する企業同士の取引事例です。本取引により、譲渡企業のジーニーは、Webサイトユーザの興味・関心に合わせた広告のパーソナライズが可能となり、広告主のブランド認知拡大・優良顧客の醸成に貢献する狙いをもっています。
ジーニー、サイジニアグループ/デクワス社のパーソナルアド事業について譲渡契約を締結
リビングプラットフォームとアートアシストによるM&A
2021年11月に、株式会社リビングプラットフォームが有限会社アートアシストの所有する介護事業の一部を譲り受けたM&Aの事例です。本取引は、事業譲渡のスキームが用いられましたが、取得価額は公開されていません。
譲り受け企業である「株式会社リビングプラットフォーム」は、介護事業・障がい者支援事業・保育事業・グループ会社の経営管理などを展開している企業です。一方の譲渡企業である「有限会社アートアシスト」は、同じく介護事業を手掛けている企業になります。
本件M&Aは、グループホーム事業も手掛ける介護事業運営会社と介護事業者による取引事例です。本取引により、リビングプラットフォームは、新たに拠点ができることで、千葉県内におけるドミナント戦略の強化を図り、今後グループの事業拡充を目指しています。
リビングプラットフォームの連結子会社、アートアシストの介護事業の一部を譲受けへ
M&Aの事業譲渡におすすめのコンサルティング会社
最後におすすめのM&Aコンサルティング会社を紹介していきます。
M&A HACK
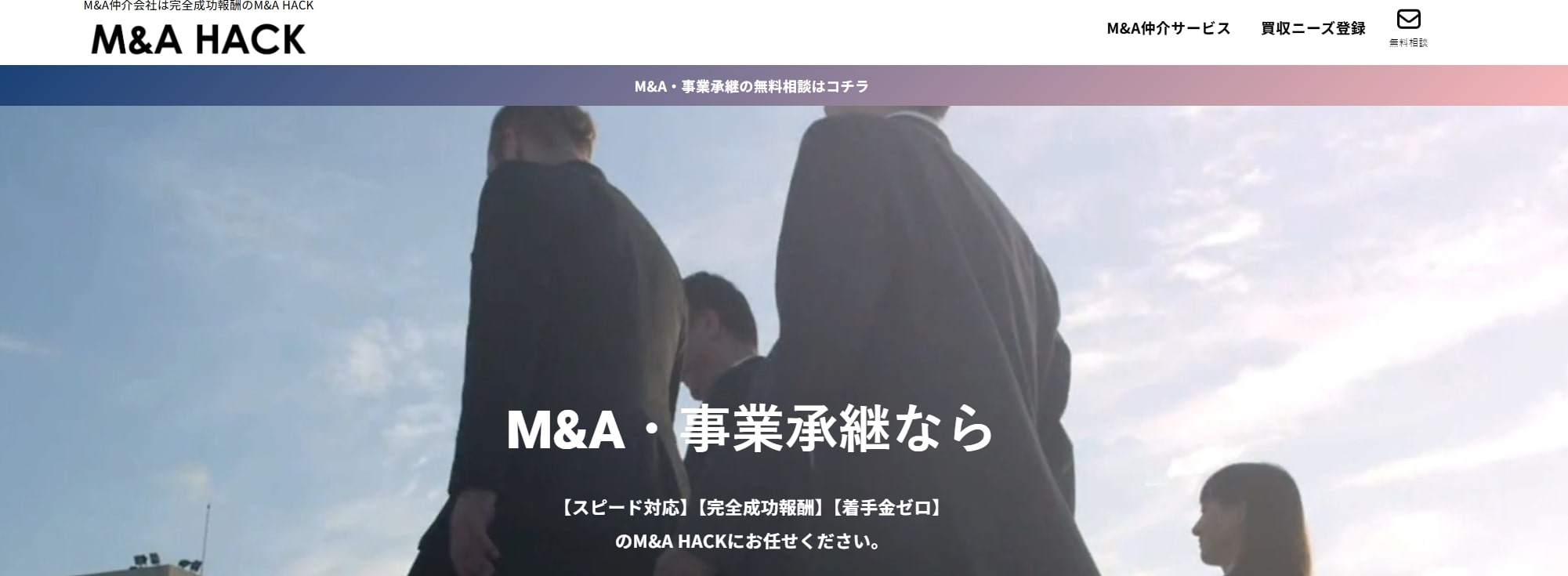
| 会社名 | 合同会社SFS |
| 設立 | 2022年12月 |
| 本社所在地 | 東京都台東区千足1-14-9 レアライズ浅草2 4F |
| 公式サイト | https://sfs-inc.jp/ma/ |
M&A HACKは、当社「合同会社SFS」が運営するM&Aコンサルティング会社です。2022年の設立から既に多くのお客様に依頼をいただいています。
当社は「スピード対応」「完全成功報酬制」「リスクなし」の3つをコンサルティングの軸としているのが特徴です。M&A取引をスムーズにすすめながらも、完全成功報酬制を採用することで、お客様の負担を最小限に抑えることをモットーとしています。
M&Aの複雑なプロセスも、当社であれば一気通貫して徹底サポートすることが可能です。もちろん相談は無料で行っているので、ぜひお気軽にご相談ください。
無料相談のご予約:https://sfs-inc.jp/ma/contact
山田コンサルティンググループ

| 会社名 | 山田コンサルティングブループ株式会社 |
| 設立 | 1989年7月 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館10階 |
| 公式サイト | https://www.yamada-cg.co.jp/ |
山田コンサルティンググループは、1989年の設立以来長きにわたってM&Aコンサルティングを行ってきた老舗企業です。創業30年以上経過していることから、業界トップクラスの取引実績を持ちます。
山田コンサルティンググループの特徴は、大企業のM&Aのみならず、中小規模のM&A依頼も柔軟に請け負ってくれる点です。全国に支店を展開しているため、地域を問わず相談を行うことができます。
またM&Aコンサルティングの依頼以外にも、アドバイザりー業務も展開しているのが特徴です。コンサルティングとアドバイザリーの両視点から、より適切で確度の高いサポートを行ってくれます。
日本M&Aセンター
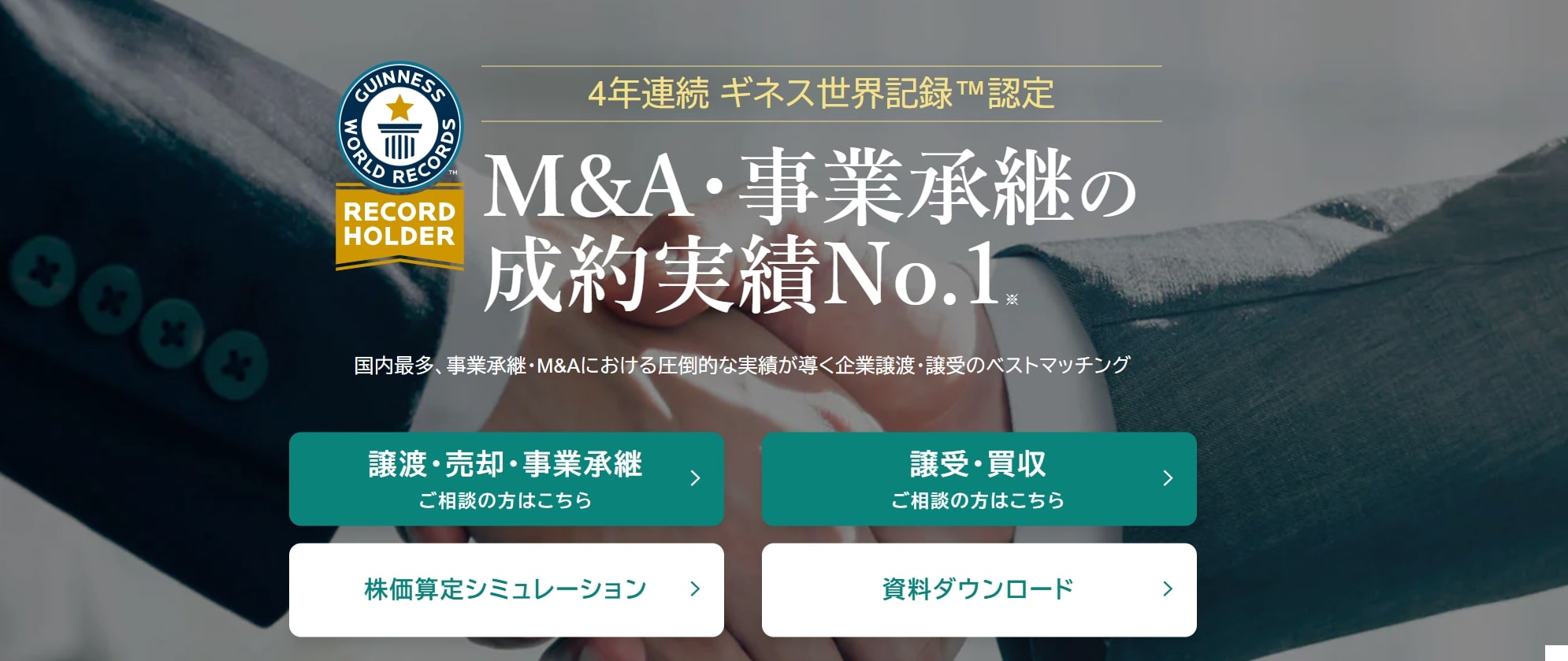
| 会社名 | 株式会社日本M&Aセンター |
| 設立 | 2021年4月 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
| 公式サイト | https://www.nihon-ma.co.jp/ |
日本M&Aセンターは、東京都千代田区に本社を置く大手M&Aコンサルティング会社です。豊富な実績と優れたコンサルタントを抱えており、業界でも高い知名度を誇ります。
日本M&Aセンターの成約数は、8500件超となっており、3年連続でギネス記録「M&Aファイナンシャルアドバイザー業務の最多取り扱い企業数」に認定されているほどです。
豊富な実績からも分かる通り、取り扱うジャンルの幅が非常に広く、あらゆる業界・取引におけるノウハウを所有しています。またM&Aコンサルティング会社でありながら、金融機関とも連携しているため、M&Aにおける資金面でも確実なサポートをおこなってくれます。
M&Aキャピタルパートナーズ

| 会社名 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
| 設立 | 2005年10月 |
| 本社所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー36階 |
| 公式サイト | https://www.ma-cp.com/ |
M&Aキャピタルパートナーズは、2005年の設立以来、譲渡株価総額2,565億円、じょうときぎょうの売上高4,462億円などの実績を誇るM&Aコンサルティング会社です。
「株価レーマン方式」を採用しており、取引価格に応じて手数料を設定しています。そのため、支払い手数料がリーズナブルであることが魅力です。余計なコストを抑えながら、コンサルティングを依頼することができます。
また同社には仕業を所有するコンサルティングが多数在籍しているのも特徴です。それぞれの分野に特化したコンサルタントが在籍しているので、幅広い分野の案件に対して柔軟に対応することができます。
インターリンク

| 会社名 | インターリンク株式会社 |
| 設立 | 2010年8月20日 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
| 公式サイト | https://www.interlink-ma.co.jp/ |
インターリンクは、2010年に設立されたM&Aコンサルティング会社です。主に提携型M&A仲介の専門会社として豊富な実績を持っており、個々の企業に合わせた独自の提案をおこなうこで、潜在的なニーズの顕在化を支援してくれます。
インターリンクは、「仲介型」のM&Aコンサルティング会社であるため、仲介者として双方の企業との信頼関係を築くことを重視しているのが特徴です。M&A取引において当事者間の認識に齟齬が発生しないよう、確実に取引を進行させてくれます。
一つのジャンルや業界に特化していない反面、あくまで独立・中立役であることに重きを置いているのがインターリンクの特徴です。そのため、純粋に案件を成立させるためにのみ、注力してくれます。
まとめ
今回はM&Aの事業譲渡についてメリット・デメリットなどを解説しました。M&Aは経営戦略として非常に有効な手段であり、実際にM&Aを実施することによって、大きく事業を発展させたり、経営を立ち直らせた企業は多く存在します。
そしてM&Aの成功には、M&Aコンサルティング会社の存在が欠かせません。M&Aコンサルティング会社を活用することで、M&Aに知見や経験がない企業も自社にメリットのあるM&A取引を結ぶことができます。
当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。
無料相談のご予約:
https://sfs-inc.jp/ma/contact