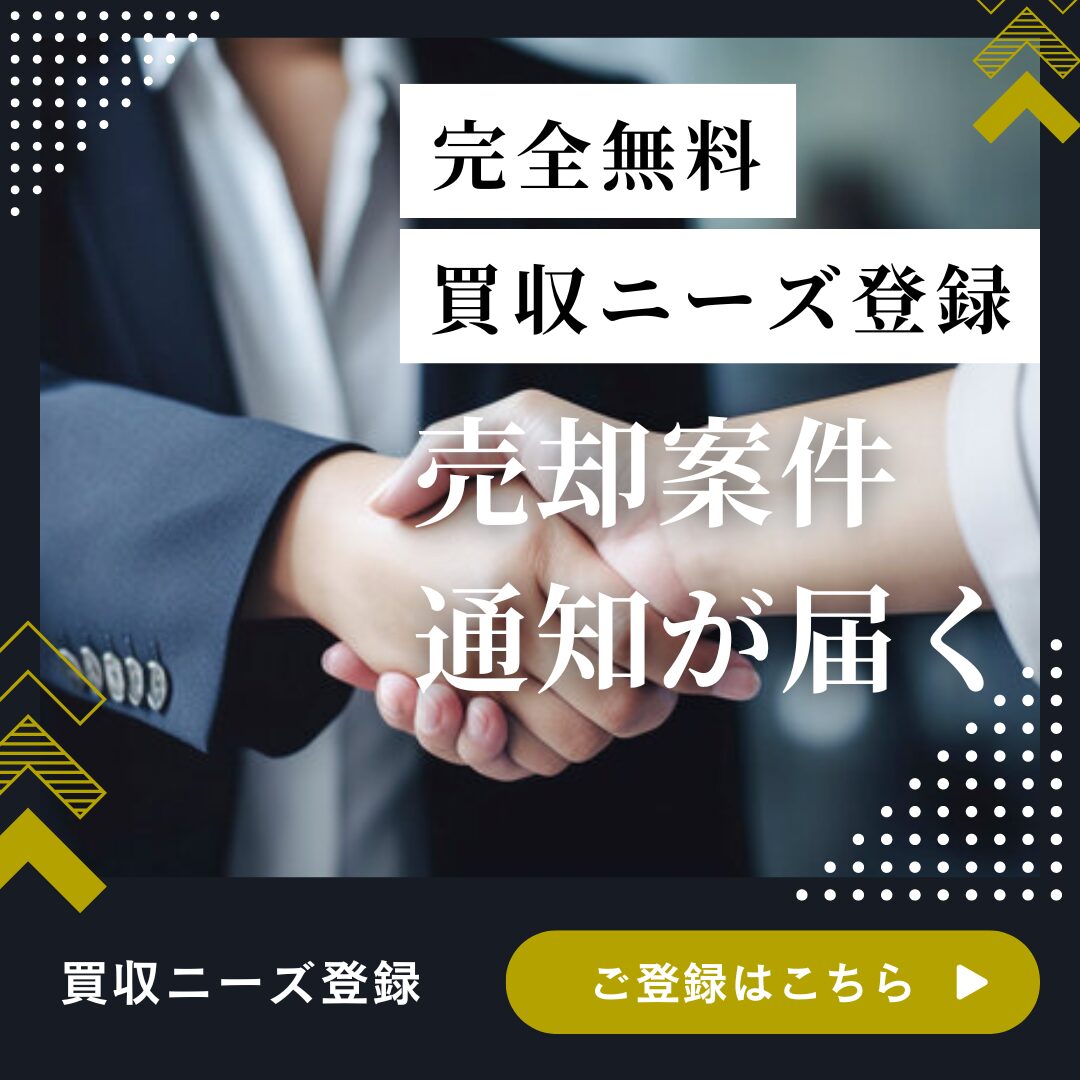「高いスキルを持つ技術者が欲しい」
「後継者がいない」
「AIに仕事を奪われるのでは?」
「電子申請の対応にはコストがかかる」
今後、ますます顕著になっていく建築指定確認検査機関が直面している課題。
この記事をご覧になっている方は、このような問題にお悩みではないでしょうか。
まちづくりやインフラ整備において欠かせない役割を担っている建築指定確認検査機関。
近年、経済や社会などの周辺環境の変化に伴い、これらの企業も従来型の戦略ではなく、日々、新しい戦略がほかの業界と同様に求められています。
生き残りをかけて、建築指定確認検査機関の多くの企業がM&Aを積極的に活用し、事業規模の拡大や効率化など、従来型の経営からの脱却を図っています。
M&Aや事業承継は、単に企業の規模を拡大するだけでなく、新たな技術や市場へのアクセス、さらには経営資源の最適化を実現する手段です。
また、後継者不足や技術革新のスピードに追いつけない中小企業にとって、事業承継は存続のための重要な選択肢の一つなのです。
しかし、M&Aや事業承継は複雑でリスクも伴うため、成功には慎重な準備と戦略が必要です。
今回、M&Aの専門企業である「M&A HACK」が、建築指定確認検査機関におけるM&Aと事業承継の全体像を明らかにし、成功のためのポイントを徹底的に解説します。
さらに、売却相場の理解から実際の成功事例までを幅広くカバーすることで、今後、直面する可能性がある課題への理解を深め、実際の取り組みに役立つ情報を提供していきます。
建築指定確認検査機関におけるM&Aや事業承継に興味を持つ企業経営者や関係者の皆様が、この記事を通じて、M&Aに対してさらに良い意思決定を行うきっかけとなることを期待しています。
目次
建築指定確認検査機関のM&A戦略の利点と重要性

建築基準法などの法律に基づく規制を遵守し、建物がその基準に合致しているかを検査する業務を行う建築指定確認検査機関は、建築物の安全性と品質を保証するためには不可欠な存在です。
BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)技術の導入により、設計から施工、さらには建築物の運用・維持管理に至るまで、一貫したデータ管理が可能になり、効率性と品質の向上が図られています。
さらに、建築確認検査の電子化、コロナ禍で活用された遠隔検査の導入、業務の自動化・AI活用など、デジタル技術の活用も必要性が増しています。
しかし、これらの取り組みには大きな投資や時間が必要であり、すべての企業が自社だけでこれらを実現することは難しいのが現状です。
そこで、M&Aが有効な戦略となります。
建築指定確認検査機関にとって、M&A(合併および買収)を行う利点は多岐にわたります。以下に、主な利点を挙げます。
- 市場シェアの拡大:
M&Aにより他の建築指定確認検査機関を取り込むことで、市場シェアを拡大し、競争力を高めることができます。 - 事業の多角化:
異なる専門分野や地域に展開している指定機関を買収することで、事業の範囲を広げ、リスクを分散することが可能になります。 - 新規事業への進出:
新しい技術やサービス領域への進出を図る際、既存の事業を持つ指定機関を買収することで、市場への参入障壁を低減し、事業展開を加速させることができます。 - コスト削減と効率化:
買収によって、検査プロセスだけでなく、営業活動、管理部門などの業務を統合し、コスト削減と効率化を図ることができます。 - 専門知識を持つ人材と技術の獲得:
優秀な人材や特定の技術・ノウハウを持つ企業を買収することで、それらを自社に取り込み、競争力を高めることができます。 新規市場への進出:
異なる地域やセクターに特化した検査機関を買収することで、新規市場への進出がしやすくなります。- 規模の経済:
企業規模が大きくなると、購買力が増し、様々なコストを抑えられる場合があります。また、大規模プロジェクトを獲得しやすくなる可能性もあります。
このように、M&Aは多大なリソースと時間を要する大きな取り組みですが、戦略的に行われた場合、企業の成長と発展に大きな貢献をもたらす可能性があります。
しかし、M&Aを行うことは、数多くのメリットがありますが、もちろん、M&Aはリスクも伴います。
異なる企業文化の融合、経営資源の適切な配分、経営戦略の一致など、成功するためには慎重な計画と実行が求められます。そのため、M&Aは一時的な成長戦略ではなく、中長期的な企業戦略の一部として位置づけるべきです。
このように、時間を買うM&A戦略は、急速な変化に対応する有効な戦略の一つなのです。この記事では、建築指定確認検査機関のM&Aについて様々な視点から詳しく紹介していきます。
それでは、まず、建築指定確認検査機関の概況や直面している課題について説明していきます。
建築指定確認検査機関の概況・課題

建築指定確認検査機関の概況と主なプレーヤー
建築基準法に基づいた建築確認申請の審査、中間検査、完了検査などを第三者検査機関として実施し、建築物の安全性と品質を保証するための業務を行う建築指定確認検査機関。
建築基準法に基づき、一定規模以上の建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないことになっています。この審査や検査は、建築物が法令上の基準を満たしていることを確認するために行われます。
指定確認検査機関は、国土交通大臣が指定した民間法人です。指定確認検査機関は、建築基準法に基づき、以下の検査を行うことができます。
- 確認検査:
建築物の設計図書及び確認申請書に基づき、建築物が法令上の基準を満たしているかどうかを検査します。 - 中間検査:
建築工事の進捗状況に応じて、法令上の基準に従って施工されているかどうかを検査します。 - 完了検査:
建築工事が完了した段階で、法令上の基準を満たしているかどうかを検査します。 - 仮使用認定:
建築物が完成する前に、仮に使用することを許可するための検査を行います。
建築指定確認検査機関では、専門的な知識と経験を持つ建築士等の検査技術者が所属し、厳正かつ中立的な立場で検査を実施しています。
以下は、主な建築指定確認検査機関です。
建築指定確認検査機関が抱える課題と解決策
一般的な課題と解決策
それぞれの解決策
課題
- 紙ベースの業務フロー:
建築確認・検査業務は、申請書類や検査報告書など多くの書類を扱うため、紙ベースの業務フローが依然として主流です。そのため、書類の保管や検索に時間がかかり、作業効率が低下しています。また、書類の紛失や誤記のリスクも高くなります。 - 複雑な法令:
建築基準法は改正が多く、複雑な内容となっています。そのため、検査員は常に最新の法令を理解しておく必要があり、業務負担が大きくなっています。 - 専門性の高い知識・技能:
建築確認・検査業務は、専門性の高い知識・技能が必要とされます。そのため、DX化を進めるためには、検査員のスキルアップも必要不可欠です。 - システム導入コスト:
DX化には、システム導入や運用のための費用がかかります。中小規模の指定検査機関にとっては、大きな負担となる可能性があります。 - セキュリティ対策:
建築確認・検査に関わる情報は、個人情報や建築物の構造に関する情報など、機密性の高い情報が含まれています。そのため、DX化を進める際には、セキュリティ対策を強化する必要があります。
それぞれの解決策
- 業務フローのデジタル化:
申請書類や検査報告書などの電子化、オンラインによる申請・検査受付、検査結果の電子化など、業務フローのデジタル化を進めることで、作業効率を大幅に向上することができます。 - 法令情報データベースの整備:
最新の法令情報を網羅したデータベースを整備することで、検査員が法令を簡単に検索・確認できるようになります。また、法令改正があった際には、自動的に通知を受ける仕組みを導入することで、常に最新の情報に基づいた検査を行うことができます。 - eラーニングツールの活用:
eラーニングツールを活用することで、検査員の知識・技能を効率的に向上させることができます。また、オンラインでの研修会などを開催することで、場所や時間にとらわれずに研修を受けることができます。 - 補助金等の活用:
国土交通省では、DX化を支援するために様々な補助金を設けています。これらを活用することで、システム導入コストの負担を軽減することができます。 - クラウドサービスの活用:
クラウドサービスを活用することで、システム導入や運用にかかるコストを削減することができます。また、セキュリティ対策もクラウドサービス事業者によって行われるため、自社でセキュリティ対策を行う必要がありません。
さらに、国土交通省は、建築確認制度のデジタル化を推進しており、その中核となるのが「電子申請受付システム」の構築です。このシステムは2025年の供用開始を目指しており、建築行政情報センター(ICBA)が実施主体となって準備が進められています。
このように、建築基準法に基づく指定検査機関のDX化には、多くの課題が存在しますが、解決策も様々にあります。国や自治体、指定検査機関、民間企業などが連携して取り組むことで、DX化を推進し、建築確認・検査業務の効率化や安全性向上を実現することができるでしょう。
このDX化においてもM&A戦略が有効な手段となります。
出典・参考:
建築行政のデジタル化対応について- 国土交通省
建築:建築確認等手続きの電子化について – 国土交通省
電子申請・電子報告関連情報 | 一般財団法人建築行政情報センター ICBA
建築指定確認検査機関がM&Aをするメリット

建築指定確認検査機関のM&Aにおいてのメリットを売却側・買収側の両方から解説します。
| 売却側のメリット | 買収側のメリット |
|
|
売却側のメリット
建築指定確認検査機関における売却側のメリットは、以下のとおりです。
- 後継者不足の解消
- 従業員の雇用継続
- 資金調達・オーナーのEXIT
- 事業の選択と集中
- 借入における個人保証の解除
それぞれ詳しく解説していきます。
後継者不足の解消
中小規模の建築指定確認検査機関にある問題として、後継者不足による廃業が挙げられますが、M&Aを進めることで後継者不足の解消に繋げることができます。
実際に後継者不足解消のため、中小規模の事業者が大手企業に会社を譲渡をすることで、後継者問題の解消に繋げるケースがあります。
また、会社を譲渡することで譲受企業から経営陣を迎え、これまで通り会社を存続させることが可能となります。
この場合、大手企業の経営者クラスに位置する優秀な人物が譲渡先の経営者となるため、譲渡した企業の事業規模はこれまでより拡大される可能性が高くなります。
後継者不足に悩んでいる企業にとって、会社の譲渡・M&Aを行うことは廃業を避けるための大きな手段のひとつです。
従業員の雇用継続
売却側の企業が廃業目前であった場合、M&Aを実行することで、既存従業員の雇用を継続して守ることができます。実際にM&Aを行った場合、ほとんどのケースで譲受企業によって従業員の雇用が継続されています。
労働条件においても引き継がれるケースがほとんどなので、既存従業員が被る影響は、廃業と比較してかなり大きく抑えることができます。
給与待遇や労働条件が同じであれば、M&A後の離職率も低い水準のままだと考えられます。
待遇面においては、M&A後に給与受験・労働時間・年間休日・福利厚生などの改善が行われるケースも多くみられます。
M&A以前よりも好条件で雇用されるケースもあるため、既存従業員にとっては大きなメリットとなり得ます。
資金調達・オーナーのEXIT
当然ながらM&Aによって売却された企業は、買収側の企業より金銭的収入を得ることができます。これは売却側のオーナーにとって大きなメリットとなります。
M&Aによって獲得した現金の使い道としては、代表的なものとして以下のものが挙げられます。
- 残っている借入金の返済に充てる
- オーナー自身の引退後の生活資金とする
- 新規事業における資金源とする
もし、M&Aをせずに廃業となれば、有形資産を処分する費用や解雇する従業員への補償など、多くのコストがかかります。オーナーにとっては廃業を選ぶよりM&Aを選ぶことの方が、はるかにメリットは大きいでしょう。
事業の選択と集中
景気悪化が続いてきた日本では、生き残りのために複数以上の事業を多角展開する企業も珍しくありません。しかし事業の多角化は一歩間違えれば、赤字を生み出し、廃業の原因になる可能性があります。
M&Aのスキームの一つである「事業譲渡」によって、不要となった事業やその関連資産だけを選別して売却することが可能です。実際に事業譲渡で、特定の事業だけを他社に売却する企業は数多くあります。
M&Aの事業譲渡によって事業を売却し、得意分野に資金や人員を集中することで、経営状態の好転にもつながる可能性もあります。
借入における個人保証の解除
借入による資金調達では、当然ながら返済義務が生じ、返済ができない場合は個人資産を失うことになります。建築指定確認検査機関だけでなく、全ての経営者にとって大きな精神的負担となります。
特に中小規模の建築指定確認検査機関の場合、経営資金の融資調達はオーナー経営者が個人保証したり、個人資産を担保に入れることがほとんどのはずです。倒産や廃業に陥った場合、オーナー個人の損害は甚大なものとなります。
M&Aで会社を売却することで、会社は廃業や倒産を免れるだけでなく、基本的に債権も買い手に引き継がれるため、個人保証や担保差し入れを解消することができます。
オーナーが持っていた大きな悩みの種をすべて解消することに繋がるのです。
買収側のメリット
M&Aにおける買収側のメリットは、以下の通りです。
- 事業拡大のチャンスになる
- 新規事業へのハードル削減
- 優秀な人材の確保
それぞれ詳しく解説していきます。
事業拡大のチャンス
M&Aにおいて買収側が得られる最大のメリットは、事業拡大のチャンスを得ることです。M&Aによって買収側の企業は規模やシェアの拡大を達成することができます。
建築指定確認検査機関のM&Aにおいては、売手となる企業が持つ設備や不動産のような有形資産に加え、顧客・取引先・各種情報などの無形資産を手に入れることも可能です。
また、中小企業双方のM&Aは市場シェアを拡大させ、ライバルに圧倒的な差を付けることにも繋がります。
新規事業参入へのハードル削減
買収側企業は、新規事業や新規分野への参入を迅速に行うためにM&Aを実行することもあります。
ゼロから内部の資源だけで新規事業を構築するよりも、買収によって事業そのものを買うことのほうが、はるかに早期の進出が可能となります。さらに、M&Aによって新しい事業を買収し、複数以上の事業展開によるリスク分散も可能となります。
このように、売却先の企業が持つノウハウや市場シェアをそのまま引き継ぐことができる利点を持ったM&Aも、ここ数年で一気に増加しており、結果として、新規事業への投資額は減少し、参入コストと時間が削減されることで、早期の段階で利益を確保できる結果を生んでいます。
優秀な人材の確保
少子高齢化が問題となっている現代では、優秀な人材の確保がどの業界においても必須の課題です。
M&Aを行うことによって、売却側企業に所属する従業員をそのまま雇用すれば、優秀な人材をそのまま自社に引き入れることができます。業界におけるノウハウも既に所有しているため、研修を行う手間も省くことが可能です。
ただ、売却側企業の従業員がすべて優秀であるとは限りません。また、M&A後の企業文化の変化に追いつかず、離職する従業員が発生する可能性もあります。
M&Aによって従業員を引き継ぐ場合、この点に繊細な注意が必要です。
建築指定確認検査機関におけるM&Aの注意点

建築指定確認検査機関のM&Aを行う際の注意点として、競業避止義務について説明していきます。
建築指定確認検査機関のM&Aにおける競業避止義務
建築指定確認検査機関のM&Aにおいて最も留意すべきポイントとなるのが、「競業避止義務」です。競業避止義務とは、一般的に「一定の者が自己(自社)または第三者の利益を損なうような取引をしてはならないこと」と定義されます。
以下が留意すべき点です。
- 情報の非公開化:
M&Aに関わる企業は、取引の過程で得た相手方の機密情報や営業上の秘密を外部に漏らさない義務があります。これには、製品開発や戦略・顧客リストなどが含まれます。 - 事業活動の制限:
M&A後、特に買収された側の企業の経営者や重要な従業員は、一定期間、同業他社で働くことや新たに競合する事業を立ち上げることが制限される場合があります。買収した企業の投資価値保護のためです。 - 顧客やサプライヤーとの関係:
M&Aを通じて得た顧客やサプライヤーとの関係を利用して、不当な競争優位を得る行為を避ける義務があります。これには、不公正な価格設定や市場独占の形成を防ぐことが含まれます。 - 市場への影響:
M&Aによって既存市場の様相が大きく変化し市場の競争が不当に制限される可能性があります。これは消費者の利益を毀損することにつながるため、適切な市場分析と関係者間や監督官庁と調整を行う必要があります。 - 従業員の扱い:M&Aで発生する可能性がある従業員の解雇や職務の変更に際して、公平な手続きを行う義務があります。これには、適切な通知期間の提供や、必要に応じた再教育・再配置の支援が含まれます。
建築指定確認検査機関に限らず、M&Aを行う際は、これらの競業避止義務に留意し、適切な契約内容を定めることが重要です。
建築指定確認検査機関におけるM&Aを成功させるためのポイント
建築指定確認検査機関のM&Aを成功させるためのポイントは以下が挙げられます。
- M&A戦略の立案
- 相場価格をよく理解しておく
- 統合後のプロセス確立
これらをそれぞれ詳しく解説していきます。
M&A戦略の立案
M&A戦略とは、M&Aによってどのような効果を得るのかを検討するための準備や計画を指すものです。M&A戦略の如何によって、M&A後の事業計画もより具体化されます。
M&A戦略では、自社の分析(SWOT分析)や市場調査・業界トレンドなど様々な要素を調査することが必須です。明確な戦略を立てたうえで、買収(売却)先選定や交渉を行なっていくことになります。
M&A戦略において重要視すべきポイントは、以下の通りです。
- M&Aにより何を達成したいか(売却・売却後まで視野に入れたもの)
- 自身の企業は売れるのか。売れるとすればどの部分か(事業の一部または全部)
- いつ・誰に・何を・いくらで・どのように売却(買収)するか
- 買収(売却)において障壁となる要素はあるか
- M&Aに必要な予算はどのくらいか(買収側)
上記のポイントを押さえておくだけで、M&Aにおける戦略はより具体的なものになります。反対にM&A戦略が場当たり的だと、交渉において不利な条件を飲まされるなどの弊害が発生します。
M&Aについて自社に詳しい人物がいない場合、M&A委託業者に戦略の立案・実行を依頼することを強く推奨します。費用こそ掛かりますが、よりスムーズにM&Aを成功まで導いてくれるでしょう。
当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫で対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。
- 無料相談のご予約は「こちら」から
相場価格をよく理解しておく
M&Aを実行する際には、売り手側・買い手側ともに相場価格をよく理解しておくことが必要です。M&Aの企業売買における相場価格は、相手先の会社の価値によって算出され、事業売却・企業買収の金額目安とされます。
建築指定確認検査機関のM&Aでは、株式譲渡もしくは事業譲渡が使われることが多いです。株式譲渡と事業譲渡の大まかな相場は以下のように計算されます。
- 株式譲渡:時価純資産額+営業利益×2年~5年分
- 事業譲渡:時価事業純資産額+事業利益×2年~5年分
当然ながら事業利益が多いほどに相場価格も高騰します。実際のM&A売却における相場計算はM&A委託企業に依頼することになりますが、もし可能であれば依頼前に自社の相場を計算してみましょう。
また、売り手側であれば算出価格よりも安く予算を立て、買い手側であれば相場よりも高く予算を立てるのがポイントです。予算の算出においては、相場よりも多少のズレが発生することは、あらかじめ考慮しておく必要があります。
PMI(統合後プロセス)の確立
M&Aにおいては成約がゴールではなく、売り手側と買い手側の両者が思い描いた成長を実現させることが本当のゴールです。そこでM&AにおいてはPMI(Post Merger Integration)の考え方が重要になります。
PMIとは、いわばM&A成約後の「統合後プロセス」を指します。PMIにおける重要な要素には、以下のようなものがあります。
- 新経営体制の構築
- 経営ビジョン実現のための計画策定
- 両社協業のための体制構築・業務オペレーション
上記の点に留意しながら、PMIを立案します。PMIを綿密に行うことで、売り手・買い手の両者に発生するリスクを最小限に抑え、成果を最大化させます。
また、PMIは成約後に立案するものではなく、M&A戦略の立案時から実行すべきです。M&Aの成約には1年以上の期間を要することがほとんどなので、PMIも長期的に行うことになります。
建築指定確認検査機関のM&A成功事例とその戦略

ここまで紹介してきたように、建築指定確認検査機関におけるM&Aは、検査機関の成長戦略や市場競争力の強化を目的とした有効な選択肢です。
まず、M&Aの主なパターンを4つ紹介し、その後、具体的な事例を紹介していきます。
M&Aの4つの主要なパターン
- 水平統合:
競合する同業他社を買収し、事業規模の拡大や市場シェアの高める戦略。 - 垂直統合:
製造・販売・流通など、異なるバリューチェーン上の企業を買収し、事業の効率化を図る戦略。 - 異業種買収:
自社の事業以外の事業を展開する企業を買収し、新規事業への参入や顧客層の拡大を図る戦略。 - 部分買収:
特定の事業部門やブランドのみを買収し、必要な機能や資源だけを取り込む戦略。
ここまで説明してきたように、建築指定確認検査機関におけるM&Aは、市場拡大や事業部門の多様化のために、すでに不可欠な存在となっています。
次からは、当該企業のプレスリリースを参考に、成功したM&A事例とその戦略を紹介します。
M&A成功事例(水平統合):日本ERIの買収戦略
日本の建築指定確認検査機関大手のERIホールディングス(以下、ERI)は、近年、M&Aを積極活用した事業拡大戦略を推進しており、建築コンサルタントや設備設計など、関連分野への進出を加速させています。
この背景は、以下の通りです。
- M&Aの積極的模索:
ERIは事業推進に必要な人的資本の拡充のためにM&Aの機会を積極的に模索しています。これにより、新たな事業領域の開拓や成長戦略の強化を図っています。 - 人的資本への積極的投資:
M&Aを通じて人的資本の拡充を図り、組織の強化や競争力の向上を目指しています。人材教育や育成にも力を入れています。 - 業界のリソース的課題への対応:
M&Aを通じて業界のリソース的課題に対応し、競争力を強化しています。新たな技術やノウハウの取得を通じて、事業の拡大や革新を図っています。 - 変化への対応:
大きく変化する規制や社会環境の変化に迅速に対応するため、M&Aを活用して事業領域の拡大や競争力強化を図っています。
実際に、ERIは、2022年から2年間で以下のようなM&Aを行っています。

では、これらの事例をそれぞれ説明していきます。
道建コンサルタント株式会社の株式取得
概要:
2022年7月に北海道伊達市に本社を置く道建コンサルタントの全株式を取得し、子会社化。道建コンサルタントは、北海道を基盤とする建設コンサルタント会社として、長年にわたり地域の公共事業の円滑な推進に貢献してきた企業。
目的:
「インフラ・ストック分野の事業領域拡大」・「M&Aの積極的活用」の一環として、土木インフラ関連事業を推進することで、北海道地域の基盤整備への貢献とERIの企業価値向上を目指す。
森林環境リアライズ株式会社の株式取得
概要:
2022年8月に北海道札幌市に本社を置く森林環境リアライズの全株式を取得し、子会社化。森林環境リアライズは、北海道を基盤とする建設コンサルタント会社で、森林土木を強みに、地域の公共事業の円滑な推進に貢献してきた企業。
目的:
「インフラ・ストック分野の事業領域拡大」・「M&Aの積極的活用」の一環として、森林・自然環境の保全等への分野へ進出。北海道地域の発展とERIの企業価値向上を目指す。
日建コンサルタント株式会社の株式取得
概要:
2022年9月に北海道札幌市に本社を置く日建コンサルタントの全株式を取得し、子会社化。日建コンサルタントは、北海道を基盤とする建設コンサルタント会社で、長年にわたり地域の公共事業の円滑な推進に貢献してきた企業
目的:
北海道における土木インフラ関連事業の体制を強化し、北海道市場でのプレゼンスを向上させ受注拡大を目指す。
北洋設備設計事務所の株式取得
概要:
2023年5月に北海道札幌市に本社を置く北洋設備設計事務所の全株式を取得し、子会社化。北洋設備設計事務所は、公共建築に特化した建築設計事務所として、長年にわたり公共事業の推進に貢献してきた企業。
目的:
北海道における建築確認検査事業のシェア拡大と、グループ全体の収益基盤強化。北洋設備設計事務所の豊富な経験とノウハウを活用し、北海道市場でのプレゼンス向上を目指す。
アジアコンサルタント株式会社の株式取得
概要:
2023年10月に三重県松阪市に本社を置くアジアコンサルタントの全株式を取得し、子会社化。アジアコンサルタントは、三重県を基盤とする建設コンサルタント会社として、地域の公共事業の円滑な推進に貢献してきた企業。
目的:
近畿地方における土木インフラ関連事業の体制を強化とERIグループ全体の収益基盤強化を目指す。
出典:
- ERIホールディングス[6083]:道建コンサルタント株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 2022年7月19日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞
- ERIホールディングス[6083]:株式会社森林環境リアライズの株式取得(子会社化)に関するお知らせ 2022年7月29日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞
- ERIホールディングス[6083]:日建コンサルタント株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 2022年9月20日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞
- ERIホールディングス[6083]:株式会社北洋設備設計事務所の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 2023年5月23日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞
- ERIホールディングス[6083]:アジアコンサルタント株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 2023年10月17日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞
このようにERIは、北海道、東海地方など、重点地域における建築確認検査事業のシェア拡大を図ると共に、 建築コンサルタント、設備設計、環境コンサルティングなど、関連事業領域への参入・拡大も視野に入れていることがわかります。
これらの戦略を推進することで、ERIは事業基盤を強化し、収益拡大と持続的な成長を目指しています。
その最短距離の戦略として使われたものがM&Aなのです。
まとめ
今まで紹介してきたように、建築指定確認検査機関におけるM&Aは、自社だけでなく業界全体の成長を促す重要な手段です。
建築指定確認検査機関は拠点の拡大や関連事業の参入、事業承継などを目的として、M&A戦略を行うことは、今後は必須であるといっても過言ではありません。
まとめとして、ここでお伝えしたいことは、M&A成功のポイントは、明確な成長戦略を持つことがまず必要であるということです。
M&Aを単なる拡大戦略と捉えるのではなく、企業の長期的な目標達成にどのように貢献するかを考え、戦略を立案しなければなりません。
また、M&A後の統合プロセスにおいて、企業文化の融合や従業員のモチベーション維持に注意を払うことも、成功への鍵となります。さらに、事前のデューデリジェンス(買収前調査)を徹底することで、リスクを最小限に抑えることが求められます。
このように、建築指定確認検査機関におけるM&Aは、企業にとって大きなチャンスであると同時に、専門性のある慎重な準備と戦略的なアプローチが必要な取り組みです。
そのためにも、専門的な知見と経験を持つM&Aアドバイザリー企業である「M&A HACK」などの専門家と協力し、適切なサポートを受けながらM&A戦略を立案することが重要であることを最後にお伝えいたします。
建築指定確認検査機関におけるM&Aの可能性の検討に、この記事が少しでもお役に立てればと考えております。